 某PT
某PT職場を辞めたい…けど不安があるなぁ。
今回は、PTの退職についての記事です。特に「今まで職場を辞めたことがない」方には参考になると思います。
PTのみなさんは国家資格保持者とはいえ、人員飽和などの問題で将来に不安を抱きやすい状況にあります。
「職場をやめる」だとか「PT自体をやめる」という選択肢が、頭をよぎったことがある方も多いでしょう。
そこで今回は「PTが職場を辞めたくなる理由」や、「実際に職場を辞めてよかった」というPTさんの実例を紹介します。
理学療法士が仕事をやめたいと感じる理由5つ


まずは、理学療法士が仕事を辞めたくなる理由についてみていきましょう。
もちろん人によって理由は異なるでしょうが、主に給料や将来の不安、そして職場環境の問題などが多くみられます。それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
PTが職場を辞めたくなる理由5つ
給料が安い
理学療法士として働く中で、給料の問題は常に頭を悩ませる一因です。正確には、国家資格を取得している割には安いという感覚でしょうか。「生活はできるけど、責任と比べて割に合わない…」と思う人が多数いるのも納得できる給与レベルです。
将来への不安がある
キャリアアップが難しいと感じることも、理学療法士として働く際に将来への不安を抱かせる原因の一つです。昇進の機会が少なく、給与も長らく横ばい。家庭を持つことや夢の実現について考えるときに不安を感じてしまいます。また、理学療法士は増え続けており競争も激化しています。
理想のリハビリを提供できていない
PTとして働いていると、忙しい業務の中で「理想のリハビリ」を提供できないことがあります。施設の方針や限られた時間の中で、自分ができることには限りがあります。
理想が高いがゆえに、上司と意見がぶつかり「辞めよう」と決断する方は一定数います。



僕がいた職場の「リハ科ナンバー2」は、だいたいこういう理由でやめてますね…
職場内の人間関係に疲れた
職場内の人間関係も仕事を続ける上で大きなストレス要因となります。特に小規模な職場では、メンバーとの関係が密になりがちで、意見の食い違いやコミュニケーション不足が問題になることも。
また、リハ職は職場内での恋愛も多い業種。恋愛権系のもつれから、職場をやめようと決意する人もいます。
心身に支障が出ている
心身に支障が出るほどの疲労感やストレスを抱える理学療法士も多いです。人の人生を左右するというプレッシャーだけでなく、体力が求められる仕事。思った以上に臨床がハードなこともあります。



同僚PTも腰のヘルニアが悪化して現場を離れてましたね…
職場を辞めてよかったPTの実例


いったい、どういう理由で理学療法士は仕事をやめてよかったと感じるのでしょうか。
その多くは「理学療法士やめてよかった」「新しい職場に行ってよかった」というものです。
実例として、知人PT達の「転職先」や「辞めてよかった理由」をまとめます。以下の表のとおりです。
| PT | 職場を辞めてよかった理由 | 前の職場 | 今の職場 |
|---|---|---|---|
| Aさん | 仕事のやりがいが増えた | 訪問看護ステーション | 訪問看護ステーション |
| Bさん | 時間に余裕が出来た 新しいチャレンジが出来る | 老健の常勤フルタイム | 老健と訪看(パート掛け持ち) |
| Cさん | 視野が広がった 開業して将来への不安が減った | 病院勤務 | 色々経て独立開業 |
領域は同じだけど職場を変えた方、パート勤務へと変更した方、独立開業した方など、パターンはさまざまですね。
自分の人生の目的に沿ってさえいれば、どんな働き方でも満足感は得られるということだと思います。
それぞれの実例をさらに詳しく解説していきますね。
クリックでジャンプします
訪問看護ステーションを変えてよかった
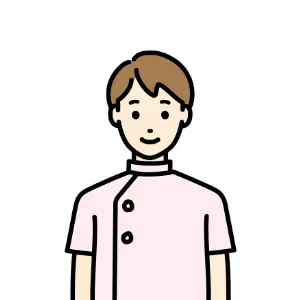
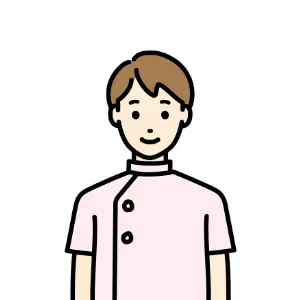
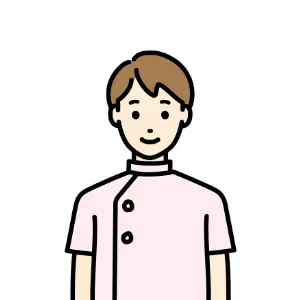
僕は、病院→訪看→訪看と職場を変えています。そして、同じ「訪看」でも、前の職場から今の職場に移ってよかったと思っています。
- 今の職場の方が、仕事にやりがいを感じる
- 業務内容的には前の職場の方が楽だった
| 前の職場:訪問看護ステーション | 今の職場:訪問看護ステーション |
|---|---|
| 介護保険がメインの訪看 利用者さんの状態も安定 仕事もゆったりめ | 医療保険がメインの訪看 利用者さんの状態が不安定なことも 臨機応変な対応が必要 |
上記のPTさんは、僕の同僚です。訪問看護ステーション勤務を2箇所経験している方なのですが、業務内容的には「楽」だった前の職場より「忙しめ」な今の職場の方が充実しているそうです。
両者の主な違いは、利用者さんの層です。介護保険の利用者さんは、状態も安定していることが多いです。なので、ゆったりとしたリハビリになりがち。逆に医療保険の利用者さんは、難病があったり、全身状態が安定していなかったりと、対応が一筋縄ではいかない場合が多いです。
医療保険メインの訪看でしか働いたことがない僕からすると「ゆったりとした雰囲気の職場っていいな」と思うものです。でも、実際に両方を経験したPTさんからすると、刺激の無さや物足りなさを感じる部分があったようです。
平たく言うと「楽な職場」よりも「多少忙しい職場」の方が、このPTさんには合ってたってことです。仕事に充実感を求めるかは人それぞれですね。
常勤からパート掛け持ちに変えてよかった
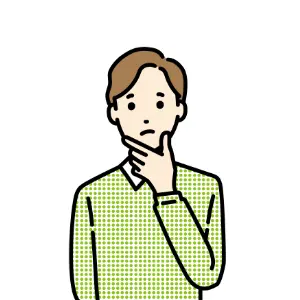
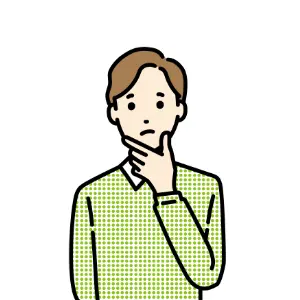
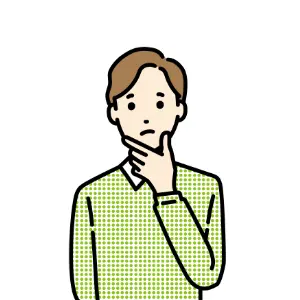
他にチャレンジしたいことがあって、老健の常勤勤務を辞めました。
そこからパートの掛け持ちをしてるのですが、自由な時間が増えたので本当によかったです。
- 雑務が減った
- やりたい勉強に専念できる
- 時間に余裕ができた
- 年収はほとんど下がらなかった
| 前の職場:老健 | 今の職場:老健と訪問看護ステーション |
|---|---|
| 老健のフルタイム常勤 | パート勤務のかけもち(老健と訪問看護ステーション) 2箇所で週5程度の勤務 |
知人PTさんの例です。この方は、もともとは病院勤務のPTさん。老健に転職後、フルタイムで働いていましたが、そこから「パート勤務の掛け持ち」へと勤務スタイルを変更しました。
勤務スタイルを変更した理由は「チャレンジしたいこと」があったから。何にチャレンジしたかったのかは、個人が特定されそうなレベルなので書きませんが、とても前向きな理由ですよね。
常勤という勤務スタイルは、リハ以外でも多くの時間を消費しがちです。この例のPTさんは「パート掛け持ち」を選ぶことで「チャレンジする時間」を捻出しました。しかも、年収は少し下がった位で、ほとんど変わらなかったとのこと。
リハ職のパート勤務は、一般的な仕事よりかなり時給は高め。特に訪問看護ステーションの歩合制はが時間効率が良いです。
年収をほとんど減らさずに、新たなチャレンジができたなら「常勤をやめてよかった」と思えるでしょうね。
※リハ職パート勤務のメリット・デメリットに関してはこちらの記事が参考になります
病院PTを辞めて独立してよかった
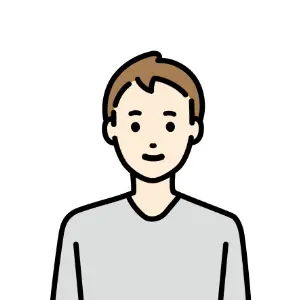
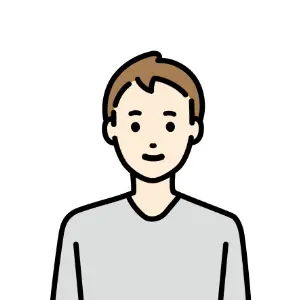
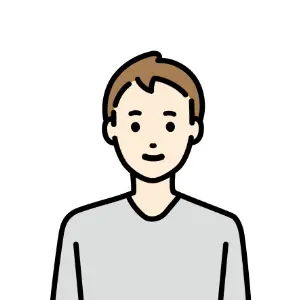
新卒で入職して、ずっと病院勤務でした。職場を辞めてから人生の視野が広がり、ついには開業・独立してしまいました。
- 新しい経験ができた
- 視野が広がった
- 独立できた
上記のPTさんは、今は独立してインソール関係の仕事をしています。もともとは新卒で入った病院に10年以上勤めていましたが、いつからか将来に不安を感じていたそうです。
自分は、同じ職場しか知らない「井の中の蛙」なのかもしれない。そんな気持ちは膨らむ一方。
思い切って病院勤務を辞めた後は、まず訪問看護ステーションやストレッチ専門店など、気になっていた職種で働きました。
電話対応に焦る自分、狭い世界にいたことを実感
実際に職場を変えてみると、自分がいかに「狭い世界」にいたのかを実感できたそうです。例えば「電話対応」。事務所にいて、お客さん(患者さん)から掛かって来ることなんて病院ではありませんよね。
最初は上手に顧客の対応できず、焦ったそうです。でも同時に「職場を変えるだけで、こんなに視野が広がるのか?!」とも感じるように。
「もっと色んな世界を見てみたい」と思った彼は、「経営者向けのセミナー」などにも飛び込んでいました。すると、また打ちのめされて視野が広がって…という感じで、結局が開業・独立までしてしまいました。
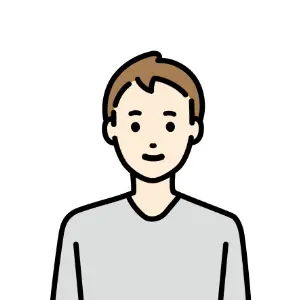
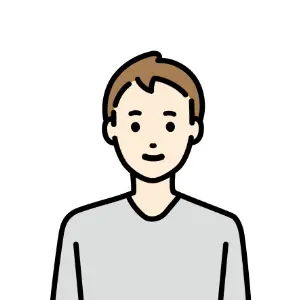
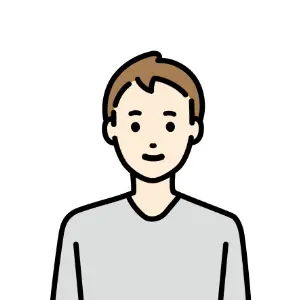
あのまま病院にいたら「井の中の蛙」でした。本当に、職場を辞めてみてよかったです。
※PTの独立・開業パターンについては下記の別記事で詳しく解説しています。


今の職場を辞めてよかった!というPTはたくさんいる


今回は「職場を辞めてよかった」というPTさんの実例を紹介しました。
紹介した方々のように、職場や職種を変えて「よかった」と思えるのは理想ですね。
なかには、同じ職場に居続けたい方もいるでしょう。だけど、動かないこともリスクになり得ることは理解しておくべきです。
- 考えがこりかたまる
- 視野が狭くなる
- その場所でしか通用しない人間になる
職場は変えたいけど、まだ転職の方針が定まってない。そんな方は、まずは転職エージェントに相談してみるのがオススメです。
特に最近はコロナ禍の影響もあって、転職市場が不安定です。
「今、求人は多いのか?」「待遇が良くなっている領域はないか?」など、まずはえージェントから情報収集しましょう。
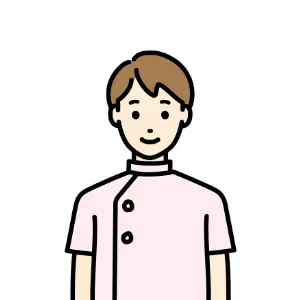
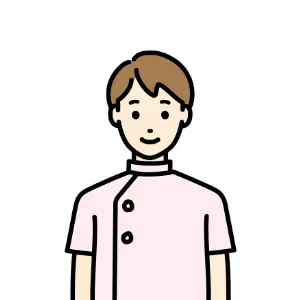
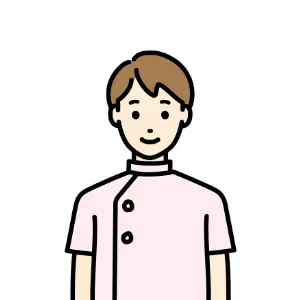
リハ転職のプロに相談すると、それだけで視野が広がります。
一度相談をしたからと言って、必ずサイト経由の転職をしないといけない訳ではないですからね。相談していくなかで、エージェントを利用するか判断すればいいです。
この記事を書いている僕も、病院勤務から転職をする際には、まず転職エージェントに相談しました。
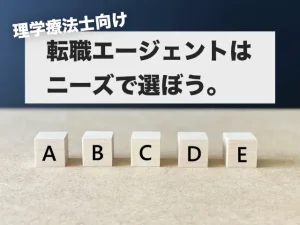
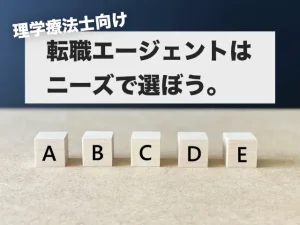
職場を辞めるということは、別の場所で働くということです。
「あのとき、あの職場を辞めてよかったな」と思えるように、万全の準備で行動していきましょう。
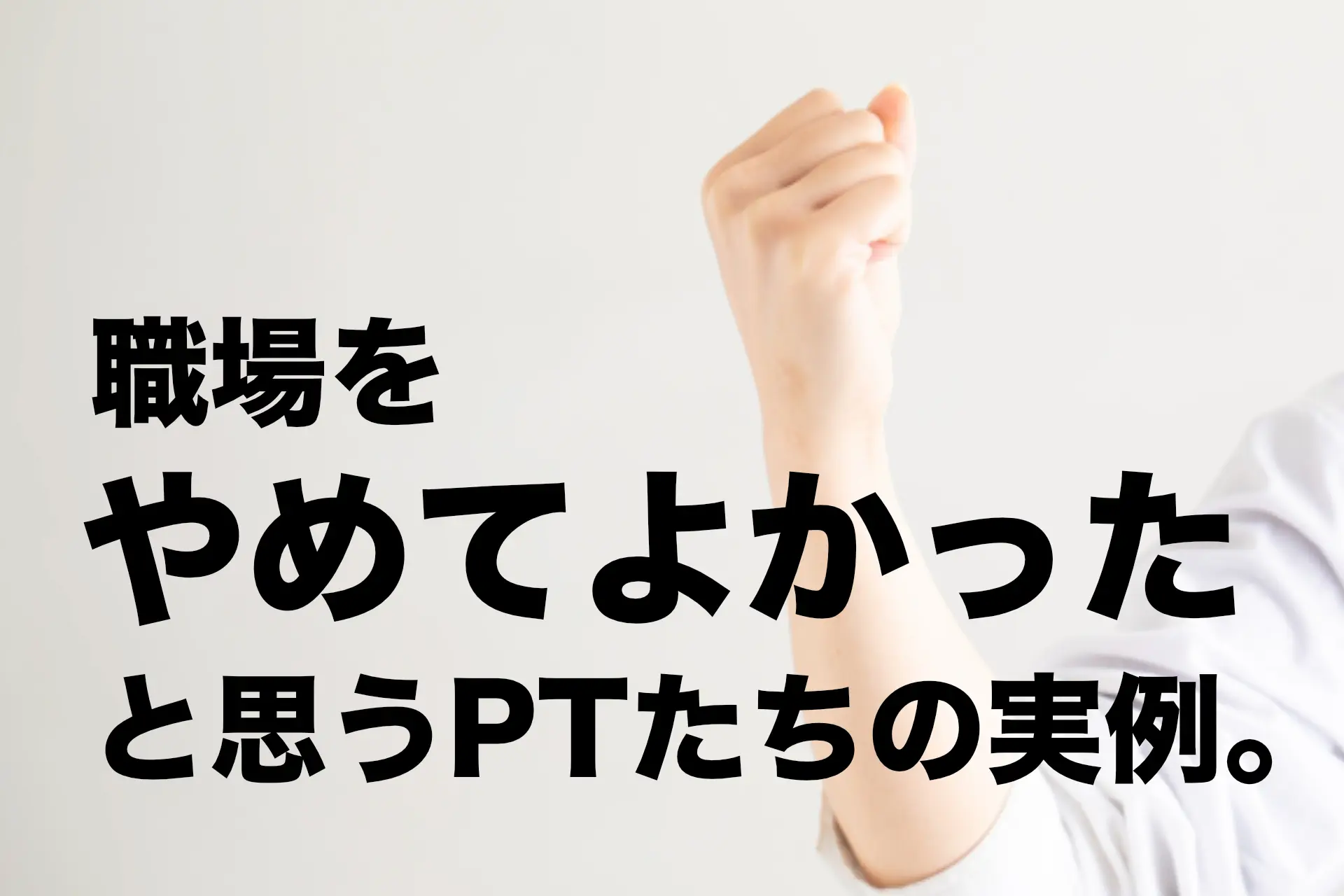
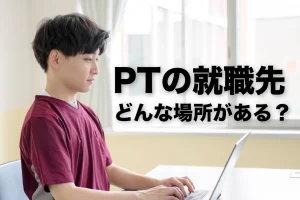
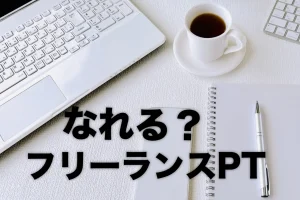


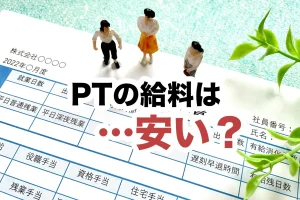
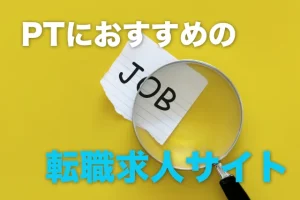


コメント